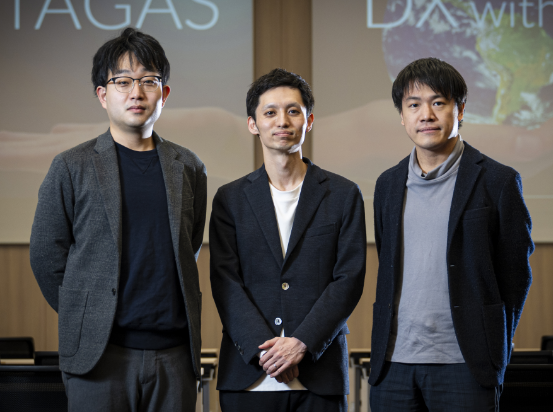our work
CEMSで理想のスマートシティをつくる
#01 地域単位のエネルギーマネジメント
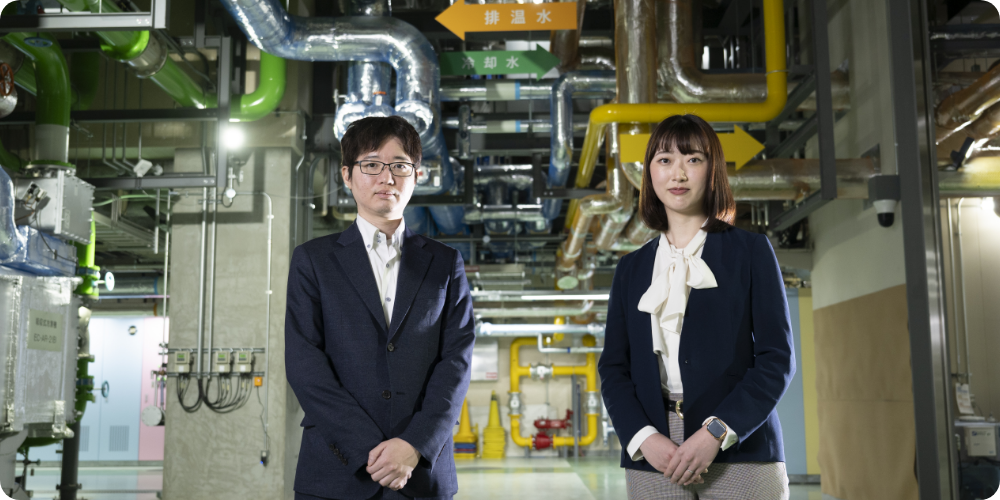
Members

萩野 伸悟
HAGINO SHINGO
エネルギーシステム部
エネルギーシステムグループ 係長
2013年入社

奥泉 文菜
OKUIZUMI AYANA
エネルギーシステム部
エネルギーシステムグループ 主任
2021年入社
Introduction
札幌の副都心・新さっぽろ駅周辺エリアが開発され、新たに生まれた街区全体のエネルギー供給を担う施設が「新さっぽろエネルギーセンター」です。当センターでは、天然ガスを燃料とする「CGS(ガスコージェネレーションシステム)」で発電を行い、同時に発生する排熱を活用して、電力・熱(温水・冷水)を街区内へ供給しています。また、AI技術を活用したエネルギーの需要と供給バランスを一括管理するシステム「CEMS」を導入することにより、必要な電力・熱の使用量を予測し、効率的にエネルギーを製造・供給することができ、街区全体の省エネにも貢献しています。
さらに、当センターではBCP時でも都市機能の維持ならびに街区全体を含めた地域のレジリエンスを強化しているほか、逆潮流可能なCGSを導入することで街区外の再生可能エネルギーの発電状況との連携ができ、再生可能エネルギーを最大限かつ効率的に活用することができるようなシステムを構築しています。この取り組みは分散型社会を構築し、省エネを推進していく当社の方針を街区単位で実現したモデルとなっています。
※BCP:Business Continuity Plan(事業継続計画)
企業が自然災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと
CEMS(セムス)とは
地域エネルギーマネジメントシステム(Community Energy Management System)の略称で、街区全体のエネルギーを管理するシステムのことを指します。当センターのCEMSには様々な機能があり、街区内への電力・熱需要量を予測し、エネルギーを効率的に管理する「需要予測」や、最適な機器運用計画を立案する「最適運転計画」、機器の効率を自動調整する「オートチューニング」、需給バランスを調整するための街区内への「デマンドレスポンス」、エネルギー使用状況の「見える化」など、街区全体の省エネに貢献しています。また、本街区では法人のお客さまへ向けた空調の省エネ制御である「自動デマンドレスポンス」を実施しており、空調快適性に関して施設利用者の声をアンケートを通じてデータ収集・分析し、回答結果を活用しながら温度緩和による省エネと過ごしやすさの最適化を図っています。

Chapter1
プロジェクトはこうして始まった
萩野 伸悟:
今のエネルギーセンターがある一帯には札幌市の公営住宅がありました。ですが、老朽化が進み解体・集約することになったため、医療や商業施設、ホテル、マンションが集まるスマートな街をつくることになりました。プロジェクトの検討がスタートした2016年当時は東日本大震災後であり、「低炭素」という言葉も世の中に浸透しはじめた頃でした。札幌市さまとしてもエネルギーの面的利用や省エネの推進、災害に強い街づくりをしたいご意向を伺っておりましたので、クリーンエネルギーの製造・供給拠点を街区内に設置し、エネルギーを効率よく管理し、省エネ運用が実現可能なCEMSを活用したエネルギーセンター方式を提案し、採用に至りました。
奥泉 文菜:
段階的なお客さまの開業に伴い、当センターの本格的な運用が始まったのは2023年でした。現在は運用管理保守、CEMS導入による省エネ効果検証、マンション入居者さま向けアプリやWEBサイトの運用・分析などが主な役割です。エネルギーセンターはプラントの完成がゴールではなく、運用・改善し続けることが重要になります。当センターで導入したCEMSは、AI技術を活用した様々な機能を有しており、中でも自動デマンドレスポンスでは街区内の法人のお客さまへ向けた空調省エネ制御であり、北ガスとして初めての取り組みでした。全国的にみても、CEMSでお客さまの空調快適性を保ちながら省エネ制御をしているというのはあまり前例がなく、お客さま側のご理解をいただくことで、省エネ運用を進めることができています。街区内のお客さまには大変感謝しております。


Chapter2
新入社員が、いきなりビッグプロジェクトにアサイン
萩野 伸悟:
プロジェクト始動当初は4名で検討を進めており、私は基本計画の段階から、メインで担当する上司のもとでプロジェクトに関わっていました。プラント設計が本格化する段階で上司が異動となり、技術的なメインの担当を私が引き継ぐことになりました。他現場でエネルギーセンター建設の経験はありましたが、リーダー的な役割は初めてだったので、少し戸惑いはありましたね。
奥泉 文菜:
私は入社後初めての配属先業務で、新入社員でも北ガスの一大プロジェクトに参画できるという喜びと、私にできるのだろうかという不安が入り混じっていました。
萩野 伸悟:
奥泉さんは本当によく頑張ってくれました。途中からの参加でしたが、プロジェクトの核となるCEMSの省エネ効果検証やマンション入居者向けアプリ開発、補助金の申請対応など、多方面で活躍してくれました。
奥泉 文菜:
人に恵まれていることも実感しています。社内や関係会社さまにはスキルを持った方々がたくさんいらっしゃるので、プロジェクトを通して多くを学び、成長に繋げたいと考えていました。入社間もない頃からこのような経験を積めるのは非常に恵まれているので、どれだけ吸収できるかが重要だと思っていました。
Chapter3
コミュニケーションがあってこその省エネシステム
奥泉 文菜:
プロジェクト期間中はとにかく、関係者の方が多くて社内でも社外でもやりとりが大変でした。入社当初は名前と顔が覚えきれなくて、大変だった記憶があります。
萩野 伸悟:
工事期間がちょうどコロナ禍と重なっている時期だったので、打ち合わせは慣れないWEB会議が中心だったことも当初は戸惑いました。
奥泉 文菜:
その他で大変なことと言えば、現在も継続しているCEMSの省エネ効果検証ですね。CEMSは当社のほかの施設でも導入していますが、オートチューニングや自動デマンドレスポンスなどは前例がありません。そのため正解もなく、トライ&エラーを繰り返しながら進めています。実際にお客さまからは「CEMSで空調の設定温度を自動制御してもらえるだけで、省エネ運用しながらも、手間が省けて助かる」とのお言葉をいただけた時はとても嬉しく、大変ではあるものの、頑張って良かったと思いました。
Chapter4
過去の経験を活かした技術の集大成を、みんなに知ってもらうため
萩野 伸悟:
これまで経験した現場で「自分だったらこういうシステムにしたい」と思うことがあり、新さっぽろエネルギーセンターでは、その学びや思いを活かせるチャンスだと考えていました。CGSはより効率よく発電・熱回収できる機種を採用し、導管や熱供給などに関するそのほかの部材も、随所にエネルギー効率や省コストにつながる仕様を取り込みました。CEMSの設計も日進月歩で発展するITやAI技術に対応すべく、時代に合わせて変更可能なシステムを導入することにこだわりました。
奥泉 文菜:
当センターは、施設見学が可能なミュージアムとしての機能を持たせることで施設の「見せる化」にも力を入れています。館内では実際に機械が動く様子や電気・温水・冷水の動線を色分けしたわかりやすい見学ルートや模型、パネルを設置し、楽しく分かりやすくエネルギーについて学べるよう工夫を凝らしています。法人のお客さまのみならず、一般の小中学生のお子さまにも社会科見学の一環としてご見学いただいており、2022年6月の運用開始から、ご見学者数は累計約3,800名を超えました。(2025年2月末現在)一般のお客さまにも当社の脱炭素社会に向けた取り組みを知っていただき、エネルギーを自分事として考えていただけたら幸いです。


Chapter5
北ガスファンをつくり、スマートシティを実現する
萩野 伸悟:
メイン担当者として、責任を持って施設が運営できていることにまずは安心しています。脱炭素社会において、これからはより徹底的な省エネ活動が求められていきます。供給側と需要側が連携しながらシステムを推進する本プロジェクトは全国的に見ても省エネスマートシティの先駆けになっているのではないでしょうか。今後もしっかり取り組みを検証しながら、省エネ効果を積極的に発信し、北ガスのファンを増やしていきたいです。
奥泉 文菜:
お客さまとの関係づくりができていなければ、ご協力をいただくことはできず、このような街は生まれていなかったと思います。本当に感謝しております。
今後もCEMSの機能を進化させ、お客さまにより付加価値の高い省エネをご提案していきたいと考えております。また、当センターの取り組みをより多くの方に認知・理解してもらい、脱炭素へ向けた「省エネ」が街としての大きな魅力のひとつとなり、本街区の活性化へ貢献できたら嬉しいです。